今回私が読み返したのは1996年に出た旧版の文庫。引用のページ表記も旧版文庫のものとなっています。
もともとの単行本は1993年~94年に出ていて、橋本さんが『窯変源氏物語』を書くにあたって考えたこと、紫式部自身や光源氏の行動についての分析、などなど興味深い話がたっぷり詰まっています。
『窯変源氏』を読んでいなくても楽しめると思いますが、『源氏物語』のおおまかなあらすじは知っておいた方が良いと思います。登場人物の名前がバンバン出てきますが、注釈などはありませんので。
【1.橋本さんご自身の凄さ】
今さらなんですけども。
そもそも『源氏物語』を光源氏の一人称で、フランス映画のように再構築しよう、という発想がまずすごい。そしてそれをこうも見事に実行してしまう手腕。
この『源氏供養』では、「ながめおはします」という一語を現代語に置き換えるにあたっての非常に細かいお話が披露されていて、たった一つの言葉を訳すだけでこれだけの分析が必要なのか!と本当にびっくりします。こんなことを五十四帖分繰り返して、『窯変源氏』全14巻を書き上げられたのかと思うと……頭の体力がとんでもないなと。
紫式部は複合動詞を多用する作家らしく、この「ながめおはします」も「ながめ+おはします」の複合動詞。「ながめ」は「眺める」ではなく、「物思いに耽る」という意味で、谷崎源氏ではそのまま「物思いに耽っていらっしゃいます」と訳されているそう。
でも橋本さんは、「ながめ」よりも「おはします」の方が重要だと考えて、別の訳し方をした。
重要なのは、「物思いに耽る」ではなく、「物思いに耽って、そしてそのままそこにいた」の“おはします”の方だと思ったからです。その方が、桐壺帝という、愛する女に去られてしまった男の悲哀が、美しくなると思ったんです。 (上巻P141)
はぁぁ、なるほど。
「自分の源氏物語は原文よりもさらに原文に忠実であるようなものにしよう(下巻P387)」と考えた橋本さんは、原文には出てこない漢詩をご自分で作りもしました。
なぜ漢詩を作ることが「原文よりもさらに忠実」になるのか。
紫式部は、漢学者の娘です。『光る君へ』でも描かれているように、父親から漢文の手ほどきを受け、喜んでそれを吸収し、父から「男であったなら」と嘆かれたほどの才を見せた人。
だから、物語の中で漢詩が必要な場面が出てくれば、彼女はきっと自在に、それを書くことができたはず。でも当時、漢文は「男のもの」で、女が手を出すべきものではなかった。
漢詩の宴の場面を書いて、でも紫式部は“「女のえ知らぬことまねぶは憎きことを」とうたてあれば、漏らしつ”と、どんな詩が詠まれたかは書かなかった。
人から「生意気だ」と言われることでもあるから、私はここにそれを書き出すということはしない (下巻P391)
こう書かざるを得なかった紫式部の悔しさを思って、橋本さんはその場面に漢詩を置いた。一晩徹夜でひねり出したそうですが、「忠実」に対する執念がすごいし、物語に込められた紫式部の思いをくみ取る敏感さ、感性がすごい。
また、和歌の部分でも、一部改変したり、新しくご自分で作られたりしたそうです。源氏物語に和歌は不可欠。和歌も心理描写であり状況描写。だからなるべく読者に読んでほしい、とばさないでほしい。そのためには和歌の改変をも厭わない。
だから、やはりこの神をも恐れない私は、紫式部の作った原文の和歌を、敢えて改変してしまいました。 (P401)
なんともすさまじいですよね。
和歌や漢詩を「必要だから」で詠めてしまうのがまたとんでもないですけど。
『源氏物語』の中で和歌は非常に重要な位置を占めるものですが、専門家の間では「紫式部は歌が下手」ということになっていたそうです。(※現在もそうなのかはわかりません。橋本さんがそう聞いたことがあるらしい)
でも橋本さんに言わせれば、紫式部は天才。
その理由は、彼女が詠む人間によって、歌を書き分けているからです。 (下巻P407)
物語の中の歌はすべて「登場人物が詠んだもの」なんですから、そこには自ずとキャラが反映される。全員が全員、歌の名手なわけないですもんね。
現代の小説でキャラクターそれぞれの台詞が書き分けられるように、紫式部は登場人物に合わせて歌を書き分けた。それができるだけの「歌の才」があった。
紫式部すごい。
和歌は心理描写で、紫式部は心理描写が好き、と橋本さんはおっしゃいます。
紫式部という人は、とっても心理描写の好きな人です。同じ時代の清少納言が、「どの人がどんなものを着ていて、それがどんなに素敵だったか」を、熱をこめて書くのに対して、紫式部はほとんどそういうことをしません。 (P414)
私も服装とかまったく描写できないタイプ(あまり興味がないので日頃から観察しておらず、知識も語彙もない)なので、このくだりを読んでがぜん紫式部に親近感が湧いてしまいました。
【2.紫式部の復讐譚】
紫式部は漢学者藤原為時の娘。大河ドラマで描かれているとおり、父為時は苦労した人で、貴族とはいえかなり身分の低い家の出です。
夫となる藤原宣孝も山城の国の守で、いわゆる「受領」レベルの人。
橋本さんに言わせると、「紫式部はまず権力者の娘が嫌い」で、「皇統の娘を素晴らしい女性だとしている」そう。
光源氏の一番の敵として描かれる弘徽殿の女御や葵の上は権力者の娘で、源氏が恋い焦がれる藤壺の中宮は帝の娘です。
そして、光源氏も「権力者」の息子ではなく、帝の息子。臣籍にくだされた帝の息子は次の帝にはなれないし、藤原氏でもないから、普通なら権力の中枢には近づけない。
その光り輝く源氏の男が、時の敵対勢力を覆して権力の頂点に就くのが、源氏物語の大筋ですね。 (上巻P84)
『源氏物語』といえば「王朝の華麗な恋物語」というイメージですが、実は「藤原氏の権力を倒す源氏の物語」であり、「体制批判の物語」でもあると。
不遇な中流貴族の娘だった紫式部は、復讐譚として――また救済譚として、『源氏物語』を書いた。
大っぴらには言えない体制批判、でも、物語としてならそれを言える。物語として吐き出さなければならないほど、切実な想いを抱えていたのでしょう。
「そこに私がいる。そこに私はいたい。そこに私がいるとしたら――そうあってもいい。何故ならば、私もここで生きている」――こういう前提がなかったら、人間というものは、絶対に物語だの小説だのを書きはしないのだと思いますね。 (上巻P112)
という橋本さんの言葉が染みます。
ところで『光る君へ』では、紫式部(まひろ)と藤原道長が「結ばれない恋」みたいなことになっていますが、史実では紫式部は道長の娘彰子に仕えています。
彰子は道長と源倫子の娘。ドラマではまひろはすでに倫子のサロンに上がっているのですが、史実ではどうだったのでしょうね。この先、恋した男とあのおっとりした倫子姫の間にできた娘のもとに仕えることになるのかぁ、と思うと、今からもやもやしてしまいますが。
彰子は一条天皇の后ですが、一条天皇のもう一人の后定子に仕えたのが清少納言。定子は道長の兄、道隆の娘です。
紫式部が『紫式部日記』の中で、「あんなにしたり顔の女はいない」と清少納言のことをこきおろしているのは有名ですが、橋本さんは、「紫式部の人柄からして、あんなにきつく言うのは不思議だ」とおっしゃいます。
そして、その謎解きをする。
清少納言が中宮定子に仕えて『枕草子』でブイブイいわしていた頃、紫式部はまだ無名の少女でした。
定子は非常に教養のある女性で、清少納言たちそばに仕える才知ある女房たちと丁々発止でやり取りを楽しんだ(らしい)。だからこそ、清少納言の「才知」も輝き、「したり顔」でいることができた。
一方、紫式部が使えた彰子は定子より一回りも年下、幼くおっとりとして、そのサロンでは才知よりも「身分」や「気品」が尊ばれる場所だったよう。
紫式部は清少納言のいた「機知に富んだ」サロンに憧れ、そして自身が上がったサロンには失望したのかもしれない、だからことさらに清少納言にキツい言葉を浴びせたのかもしれない――。
『光る君へ』でも倫子のサロンがそういう感じですよね。あまり知ったかぶったり、知識をひけらかしたりせず、おとなしくしていなくちゃ……みたいな。
世をときめく道長の娘に仕えて、名ばかりは上がっても、そこでは自身の才を発揮することができず、むしろ「身分の低さ」を痛感させられるだけだったのかもしれない。
だから彼女は、「藤原氏の権力を倒す源氏の物語」を書いた。
なるほどなぁ。
【3.光源氏という“理想の男”】
橋本さんは「光源氏」のキャラクターについて、そして『源氏物語』の構成やテーマについても大変多く語ってくれています。
まずびっくりしたのが、「光源氏は、少なくとも前半においては“女を守る男”である」という視点。光源氏は美しく、頭もよく、帝の息子という血筋、身分においてもこれ以上はないぐらいの「理想の男」なわけですが、もっとも革新的な「理想ポイント」は
女を「政争の道具」にすることが当然だった“男の時代”に、「女を守る男」というありえない理想像を作り出した。 (上巻P26)
ことだそうで。
言われてみれば光の君、あの末摘花でさえ、自分の邸に住まわせて面倒を見ているわけで、「関係を持った女たち」をちゃんと養ってやるという意味では、確かに「女を守ってくれる理想の男性」なのかも。
現代の目から見れば、若紫にあんなことをするのが「理想の男」か、とも思ってしまいますが。源氏に引き取られ、「父」でもあるような男に若紫が手籠めにされるのは、たったの12歳ぐらいの時です。ショックを受けた若紫がその後「寝床から出てこない」描写がちゃんとあるのが、当時としてはすごいことだと思うけれど。
美しい理想の男だろうがなんだろうが、女は「それ」を無条件に受け入れ喜ぶわけじゃない、ってことを、紫式部は千年も前にちゃんと書いた。
源氏と明石の上との間にできた姫は時の東宮のもとに上がり、皇子を生みます。なんと彼女は10歳で妊娠、11歳で出産という勘定になっているそうで、いくら今とは時代が違うといっても可哀相すぎ&大変すぎな気がしますが、この娘の体のことを源氏はちっとも気遣わないんですね。
そんな幼い体で出産して、「もうちょっと実家でゆっくりしたい」と思う明石の姫に対して、源氏は「そのやつれた感じも美しくてそそるぞ(だからさっさと東宮のところに戻って寵愛を確かなものにしろ)」と返すんです。
いやー、そりゃ自分もおんなじくらいの年の紫の上を可愛がってたんだから、「子ども」ではなく「一人前の女性」としか見てないのかもしれないけど、「幼い娘の身を案じる父親」としての気持ちはかけらもないもよう。
前半で「理想の男」だった光源氏は、どんどんつまらない俗物のようになっていく。それを読み解く橋本さんの筆が鮮やかなのはもちろん、「光源氏をそのように描いた」紫式部の筆が、本当にすごい。
源氏の死後、宇治十帖のヒロイン浮舟は結局男たちを拒絶する。源氏という男の恋模様を通して、さまざまな女性を描き、「女の幸せってなんだろう」を模索した紫式部の結論は、「男を拒絶し、その思惑から自由になる」だった――。
上巻の最初の方で、橋本さんは面白いことをおっしゃっています。
女は「悪い男」が好きで、でもひょっとしたら、その「悪い男」が自分の手の内で敗北して行くのを見るのが、女性はもっと好きなのかもしれない……。 (上巻P39)
山崎豊子さんの『華麗なる一族』を例に上げ、「作者はこの主人公が大好きなはずなのに、どうしてこんな終わり方をするのか」と。
紫式部もまた、少なくとも源氏物語を書きはじめた時にはきっと、「光源氏」を愛していただろうに、なぜどんどんつまらない男にして、栄華という檻の中で朽ちさせていくのか。
好きだからこそ、女は――?
久しぶりに触れた橋本節、楽しかったです。
『窯変源氏物語』もちょっと読み返したくなったなぁ。全14巻、読み始めるには覚悟がいるけど、今この年になって読んだらまた、昔とは違った景色が見られる気がします。
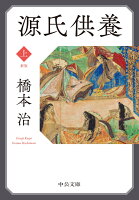







0 Comments
コメントを投稿